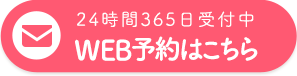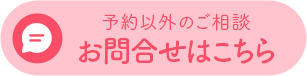性病の症状と治療について
性感染症は、性行為によって、細菌・ウイルス・原虫などの病原体に感染する病気です。少し前までは、性病と呼ばれていました。男性と比べて、女性は目立った症状が現れにくいという特徴があり、知らないうちに感染していたというケースもあります。性感染症は、パートナーにうつしてしまう可能性もあるため、注意が必要です。また、骨盤内に炎症を起こしたり、不正出血や慢性的な下腹部痛の原因になったりもします。さらに、卵管の癒着などを引き起こし、将来的に不妊症になる可能性もあります。
これらの事態を防ぐためにも、性感染症は早期発見・早期治療が大切です。「症状がないから大丈夫」というわけではなく、性行為をする機会のある女性は、定期的な性感染症検査を受けることをおすすめいたします。また、万が一性感染症にかかっていた場合には、すぐに治療をしましょう。性感染症の予防には、コンドームを使用することも大切です。
当クリニックでは、性感染症をはじめ、女性ならではのお身体のお悩みを、安心してご相談いただけるように、プライバシーに配慮した環境で診察・検査をさせていただきます。少しでもお身体の不調を感じた場合や、異変に気づかれた場合には、お一人で悩まず、まずは一度当クリニックまでご相談ください。
その日に結果がわかる即日性病検査
仙台駅前婦人科クリニックでは、検査を実施したその日のうちに結果が分かる即日性病検査を承っております。即日で検査結果が分かる性病は下記です。
- HIV感染症
- 梅毒
- B型肝炎
- C型肝炎
HIV、梅毒、B型肝炎、C型肝炎は採血検査によって感染の有無を調べます。検査結果が判明するまでの所要時間は、最短20分です。結果はLINEでご連絡しますので、お忙しい方もご安心ください。
「その日のうちに結果を知りたい」「なるべく早く検査結果が欲しい」など、検査結果をお急ぎの患者様は、お気軽に当クリニックにご相談ください。
性感染症(STD)病名一覧
| クラミジア感染症 |
クラミジア感染症は、様々な性感染症の種類の中でも、もっとも患者数が多い病気です。男性患者の症状としては、軽度の尿道炎などが挙げられ、感染に気付くことが多いです。対して女性患者には、目立った自覚症状がなく、感染に気付かない可能性があります。フェラチオやクンニリングスなどのオーラルセックスによって、喉に感染する場合もあります。 女性がクラミジア感染症にかかると、子宮内膜症や卵管炎などを引き起こすことがあり、重症になると肝臓周辺にまで炎症が生じます。その他にも、骨盤内の組織が癒着し、不妊症や月経困難症などの原因にもなるなど、様々な弊害をもたらします。 クラミジア感染症は、抗生物質を服用することで治療ができるため、定期的な検査を受け、早期発見・早期治療に努めましょう。 |
|---|---|
| 淋病感染症 |
淋病感染症は、淋菌によって生じる性感染症です。男性がかかると、出血や膿が見られ、強い痛みを伴う尿道炎を発症する可能性があります。また、女性がかかると、おりものの増加などが見られます。しかし、男性に比べ女性は、目立った症状がほとんど現れないため、感染に気付かない場合も多いです。淋病感染症は、重症化することで子宮や卵管にまで炎症がおよび、不正出血や下腹部痛が起こる原因となります。 クラミジア感染症と併発することが多く、不妊症の原因にもなることがあるので、定期的な検査を受け、治療を早く始めることが大切です。淋病感染症は、抗生物質を点滴、服用することで治療可能な病気です。 |
| 梅毒 |
梅毒は、梅毒トレポネーマによって引き起こされる性感染症です。感染から3〜6週間を経て、陰部に硬いしこりが生じます。潜伏期間が長いのが特徴のひとつです。 陰部のしこりは、治療をしなくても数週間程度で治るので、発症していることに気付かない場合もあります。その後1〜3ヶ月ほどで、手のひら・足の裏・陰部に発疹が生じ、発熱や倦怠感を伴うことがあります。梅毒は、抗生物質の服用で治療可能です。昔は抗生物質がなかったため、病気が進行し脳や神経が侵され、死に至っていました。そのため、不治の病として恐れられていました。昔の病気のイメージですが、近年では若い女性を中心に感染者数が爆発的に増えています。 |
| 性器ヘルペス |
性器ヘルペスは、性器周辺にできるヘルペスのことです。病変部と接触することによって発症するため、性行為で感染します。潜伏期間は3日〜1週間程度で、性器ヘルペスにかかると、男女ともに性器に小さな水泡ができます。口元にできるヘルペスと同様、痛い・痒いといった症状を伴います。ヘルペスウイルスは、一度感染すると、ウイルスが神経節に潜むため、完全に排除することができません。免疫力が落ちた時やストレスなどが原因で、再発することがあります。しかし、現在はヘルペスの再発を薬の服用によって抑えることができます。また、ヘルペスの感染を防ぐには、症状が出ている際の性行為を控えることが重要です。 口唇周辺のヘルペスが、オーラルセックスによって、性器に感染することもあります。性器だけでなく、口の周りにヘルペスが出ている場合にも、性行為は避けましょう。ヘルペスウイルスが口内に感染すると、ヘルペス性口内炎を引き起こす可能性もあります。 |
| B型肝炎(HBV感染症) |
B型肝炎は、70〜80%の確率で症状が現れない病気です。発熱・食欲不振・倦怠感・黄疸などが生じる「急性肝炎」を発症したとしても、ほとんどの場合は完治します。しかし、感染者の10%程度は「慢性肝炎」を発症し、肝硬変や肝臓がんの発症リスクが上昇することがわかっています。慢性肝炎には目立った症状はほとんどありませんが、肝硬変になると治療ができません。 「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓は、病気の自覚症状などがほとんど現れないため、定期的な検査を受けて、早期治療を始めることが重要です。 |
| C型肝炎(HCV感染症) |
C型肝炎にかかると、慢性肝炎・肝硬変・肝がんなどを発症する可能性があります。自覚症状がほとんどないため、B型肝炎と同様、定期的な検査を受けることが大切です。 |
| HIV感染症 |
HIV(ヒト免疫不全ウイルス)は、エイズの原因となるウイルスです。HIVに感染することで、免疫力がだんだん弱くなっていきます。HIV感染症は、治療を行わないと、数年〜10年程度で、健康な人であれば問題ないウイルスや菌によって、様々な病気を引き起こすようになります。また、他の性感染症に感染している場合には、HIVの感染率は数倍増加すると考えられています。 死につながるイメージの強い病気でしたが、現在では適切な投薬治療によって、通常の日常生活を続けることが可能になっています。 |
性感染症検査
| 即日HIV検査 | 4,000円 |
|---|---|
| 即日梅毒検査 | 4,000円 |
| 即日B型肝炎検査 | 4,500円 |
| 即日C型肝炎検査 | 4,500円 |
| 淋菌検査 | 6,000円 |
| クラミジア検査 | 6,000円 |
| STD-A 淋菌、クラミジア、HIV、 梅毒、B型肝炎、C型肝炎 |
18,700円 |
| STD-B 淋菌、クラミジア、HIV、梅毒 |
13,800円 |
| STD-C 淋菌、クラミジア |
11,700円 |
| STD-G HIV、梅毒 |
7,000円 |
| STD-H HIV、梅毒、B型肝炎 |
9,500円 |
- ※上記以外の性病検査をご希望の方は、クリニックまでお問合せください。
News
お知らせ
-
2025/01/27
2025年2月より、一部料金を改定させていただきます。
-
2025/01/24
子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種期間が延長されました。くわしくはキャッチアップ接種期間延長についてをご覧ください。
-
2023/01/05
VIO医療脱毛と膣ハイフの期間限定キャンペーン中です。